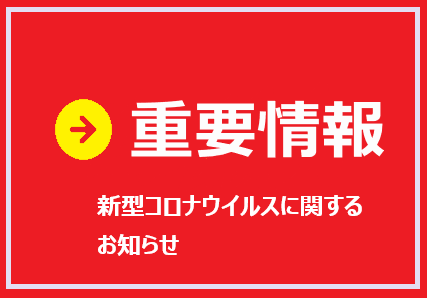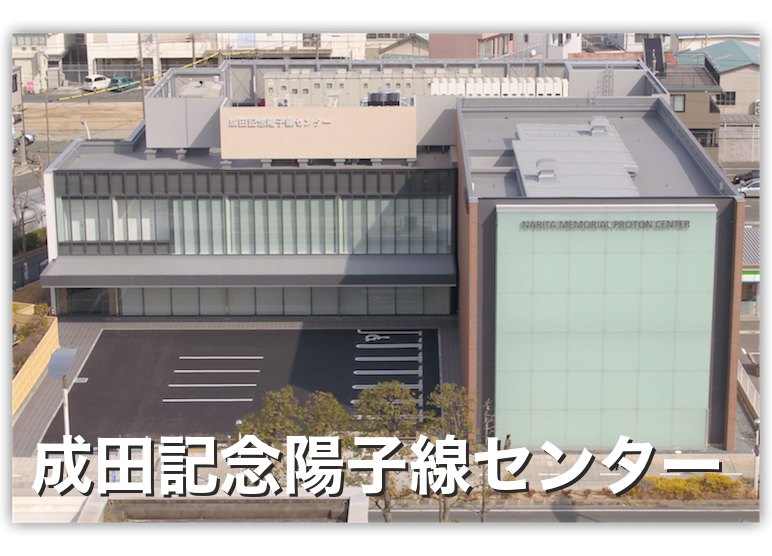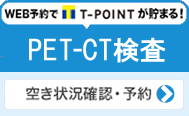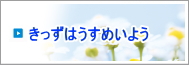医師

大沼 哲朗
昭和63年浜松医科大学卒
医学博士、日本麻酔科学会専門医
日本東洋医学会認定医
国立大学法人浜松医科大学非常勤講師

中尾 康尚
昭和63年山梨医科大学(現 山梨大学医学部)卒業
日本麻酔科学会専門医

朝田 智紀
平成17年宮崎大学医学部卒業
日本麻酔科学会専門医
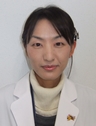
宮林 真沙代
平成17年愛知医科大学卒
日本麻酔科学会指導医・専門医、日本救急医学会専門医
主な活動内容として手術の麻酔とペインクリニックの外来診療があります。
麻酔
手術室では、手術室支援システムによる手術室の効率化をはじめ、麻酔器、患者モニター装置を充実させ、安全で高度な手術に対応出来るよう手術室環境を整備しています。全身麻酔管理は主に外科、泌尿器科、整形外科、口腔外科、眼科、耳鼻科、形成外科の手術に対して行われており、手術・麻酔の進歩とともに、実施可能な高齢者の手術も増えています。悪性腫瘍の手術や肺・心臓に合併症がある場合は、手術を受けることが決まった早期から手術に関連する多職種の医療スタッフが連携して状態を把握し、薬の管理、呼吸リハビリ、栄養指導、禁煙指導などを実施し、周術期管理の質と安全性の向上を目指した体制を構築しています。また、手術の際には、新型コロナウイルス対策など感染防御を徹底しています。
ペインクリニック
ペインクリニックでは、頭痛、顔面・口腔内の痛み、首・肩・上肢の痛み、胸・背部痛、腰下肢痛、会陰・肛門部痛、全身痛など様々な要因による痛みの治療と、疼痛に伴う様々な心理的・身体的症状に対して心身両面からの全人的医療を目指しています。主な対象疾患として、帯状疱疹後神経痛や手術後に残存する疼痛、また、慢性疲労症候群、身体症状症など機能性障害が病態となる慢性難治性疼痛があります。当科で可能な慢性難治性疼痛の治療法としては各種神経ブロック、近赤外線照射療法の他に東洋医学的アプローチ(漢方療法)、精神医学的アプローチ(認知行動療法)があります。筋・筋膜性疼痛、頚椎症・腰椎症、帯状疱疹痛のような急性痛に対しても神経ブロック療法、薬物療法を行なっています。また非疼痛性疾患では眼瞼痙攣・顔面痙攣に対してはボツリヌス毒素注射を行っています。
(2025年1月より多汗症に対して胸腔鏡下交感神経遮断術を実施しておりません。)
全身麻酔件数
| 年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔件数 | 810件 | 829件 | 1,028件 | 1,008件 | 1,044件 | ||
外来患者数
| 年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初診数 | 100件 | 106件 | 142件 | 152件 | 146件 | ||
| 再診数 | 3,003件 | 3,308件 | 3,949件 | 3,520件 | 3,183件 | ||
| 合計 | 3,103件 | 3,414件 | 4,091件 | 3,672件 | 3,329件 | ||
| 実患者数 | 1,718件 | 1,968件 | 2,136件 | 1,966件 | 1,893件 | ||
講演
●2024年12月3日 Pain Live Symposium(Web配信)
『新型コロナウイルスと帯状疱疹後神経痛』山梨大学医学部 皮膚科教授 川村龍吉先生 座長 大沼哲朗
●2024年7月30日 田原市学術講演会(渥美病院 ハイブリッド形式)
難しい痛みに対する易しい薬の使い分け~その痛みは神経障害性疼痛?それとも痛覚変調性疼痛?~ 大沼哲朗
●2024年4月17日 新城市薬医師会漢方講演会(Web配信)
冷えと痛みに使われる漢方薬について 大沼哲朗
●2024年3月6日 新城市薬剤師会漢方研修会(新城市文化会館)
かぜ・アレルギー性鼻炎に使われる漢方薬 大沼哲朗
●2024年1月30日 西尾市医師会漢方研究会(Web配信)
冷え、痛みに対する漢方薬 大沼哲朗(成田記念病院)
●2023年11月25日 慢性疼痛診療研修会
痛みの治療を知ろう 大沼哲朗
●2023年9月3日 静岡県部会学術講演会 教育講演(西尾市医師会館 ハイブリッド開催)
心の痛み、身の痛み~やっかいな痛みに対する漢方薬の役割~ 大沼哲朗
●2023年5月30日 西尾市医師会漢方研究会(西尾市医師会館 ハイブリッド開催)
「心の痛み、身の痛み」~漢方医学による痛みの捉え方・方剤の選び方~』大沼哲朗
●2023年3月11日 臨床整形外科医会(都ホテル 四日市)
「心の痛み、身の痛み」~やっかいな痛みに対する漢方薬の役割~』大沼哲朗
●2023年3月7日 浜松医科大学麻酔科医のための KAMPO Meeting(浜松アクトシティ)
「心の痛み、身の痛み」~やっかいな痛みに対する漢方薬の役割~』大沼哲朗
●2022年9月6日 痛み治療を考える会(ZOOMウェビナー配信)
『より良い生活に向けて「痛み」とどう向き合うか~ミロガバリンへの期待~』大沼哲朗
●2021年7月1日 東三学術講演会(ZOOMウェビナー配信)
『より良い生活に向けて「痛み」とどう向き合うか~ミロガバリンへの期待~』大沼哲朗
●2020年3月24日 豊川外科系医会学術講演会(豊川市民プラザ)
「神経障害性疼痛の治療薬をどのように使い分ける?~薬の長所・短所からもう一度見直して~」大沼哲朗
●2020年2月19日 東三学術講演会(ホテルアソシア豊橋)
『より良い生活に向けて「痛み」とどう向き合うか~ミロガバリンへの期待~』大沼哲朗
●2020年2月6日 桜山漢方勉強会(名古屋市立大学医学部研究棟)
「日常診療における漢方の使い方~漢方医学と西洋医学の融合・ストレス疾患~」大沼哲朗
発表
●2020年3月27日 第6回日本医療安全学会学術総会(インターネット学術総会)
「当院における多職種連携による画像診断報告書見落とし防止策」
大沼哲朗 岸田久美子 石井美砂子 吉冨裕久 川村史朗 三須義直 吉田匡登
●2020年2月21日 第25回日本災害医学会総会学術総会(神戸国際会議場)
「一般病院における携帯端末アプリケーションを用いた災害時情報伝達の構築」
川村史朗 大沼哲朗 中林吉雄 松橋宏尚
●2020年2月20日 第25回日本災害医学会総会学術総会(神戸国際会議場)
「発災後から27時間を想定した訓練からみえたもの-実働型訓練と机上訓練の連動-」
中林吉雄 大沼哲朗 川村史朗 松橋宏尚
外来診療表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 8:30~11:30 予約 |
朝田 |
大沼 |
中尾 |
朝田 |
大沼 |
中尾 |
お知らせ
慢性の痛みは難治性なこともあり、一人の治療に時間を要することも多く、お待たせすることもあり予約制となっております。また、他院で治療を受けられている方は基本的には病診連携からの紹介でお願い致します。