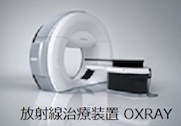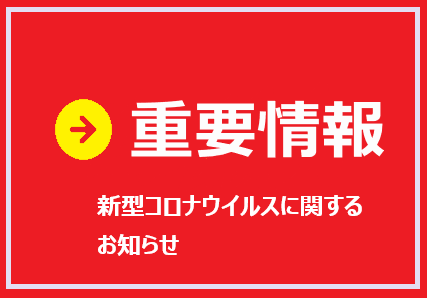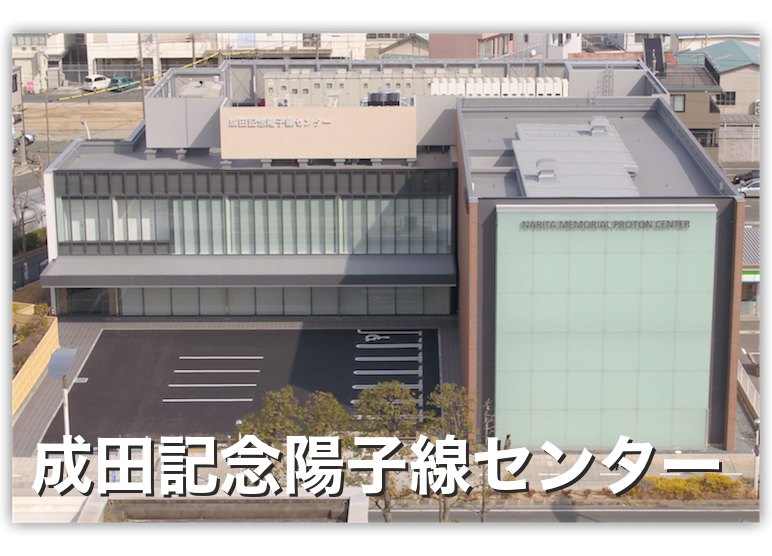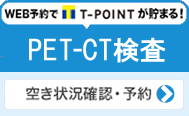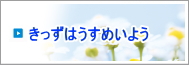輸血拒否に関する当院の方針について
当院では、宗教上の理由で輸血を拒否される患者の皆様に対して、以下のように対応いたします。何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
- ・ 当院で実施する医療行為(手術・検査などすべてを含む)において、輸血を行うことにより死亡の危険性を回避出来ると医師が判断した場合は、宗教上の理由による輸血拒否の意思表示よりも生命の維持を最優先して輸血を行います。【相対的無輸血(注1)】
- ・ 宗教上の理由による「輸血拒否及び免責に関する証明書」に類する書類は絶対的無輸血(注2)に同意するものですから署名しません。
- ・ 当院の、生命の維持を最優先する方針には、患者の意識の有無及び成年と未成年を区別しません。
- ・ 当院の方針を十分に説明し理解を頂けるように努力しますが、どうしてもご同意いただけない場合は転院をお勧めします。
注1:相対的無輸血とは患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った時には輸血をするという立場・考え方。
注2:絶対的無輸血とは、患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方。
臨床倫理の基本方針
1.倫理四原則
- ① 自己決定の尊重:患者さんの意思を尊重します。
- ② 善行:患者さんにとって善いことを行います。
- ③ 無危害:患者さんに害を与えないようにします。
- ④ 公正:限りある医療資源を公正に配分できるようにします。
2.具体的な倫理問題への対応方針
- ① インフォームドコンセント(説明と同意)
検査や治療を行う際には、患者さんが理解できるように当院の「インフォームドコンセントガイドライン」に基づき説明を行い、同意を得た上で提供します。一旦同意したあとでも、同意を撤回することができます。 - ② 意思決定が困難な患者さんへの対応
意識障害や認知症などにより本人の意思が確認できない場合には、代理人(親族や患者の意思を適切に推定できる方)に説明し、適切な判断ができるよう支援します。代理人も不在の場合には多職種で協議し、最善と思われる医療行為を行います。 - ③ 輸血拒否患者さんへの対応
宗教上の理由から輸血を拒否される場合、患者さん本人の意思を尊重することを基本としますが、輸血なしでは救命できない事態に至った場合は救命のために輸血を行うというのが当院の方針です(相対的無輸血)。この方針に同意いただけない場合は転院先をご案内します。 - ④ 身体拘束について
患者さんの安全を保ち、危険を回避するためにやむを得ない場合のみ、一時的に身体抑制を行うことがあります。抑制の3要件「切迫性(生命などが危険にさらされる可能性があること)」「非代替性(他に手段がないこと)」「一時性(身体拘束が一時的なものであること)」に基づき、多職種で協議して必要最低限の期間のみ行います。 - ⑤ 虐待について
児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待あるいは配偶者からの暴力を受けた疑いがある場合には、「成田記念病院虐待防止・対策指針」に従って対応します。 - ⑥ 検査・治療・入院の拒否、指示不履行について
患者さんは望まない治療を拒否することができます。治療を行わないことによる不利益を十分に説明したうえで方針を決定しますが、これは積極的安楽死を認めるものではありません。 - ⑦ 終末期の意思決定について
終末期医療に関しては、「人生の最終段階における医療・ケアの対応方針」に従い、患者さん・ご家族と相談しながら患者さんの意思に基づいた医療を行います。 - ⑧ 医療事故の報告と原因の究明について
医療事故が発生した場合は、すみやかに医療安全管理室へ報告し、原因の究明に努めます。重大な障害や死に至る事故が発生した場合は、事故対策本部を設置して対応を協議します。患者さんやご家族に対しては、事故の経過や原因について説明し、誠実に対応します。 - ⑨ その他の倫理的問題について
この対応方針により判断が困難な場合には、多職種から構成される臨床倫理部会にて検討します。
身体拘束最小化のための指針
Ⅰ.身体拘束最小化に関する基本的な考え方
身体拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を拒むものである。当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急・やむを得ない場合を除き身体拘束をしない診療・看護の提供に努める。また、やむを得ず身体拘束を行う場合も、常に身体拘束最小化にむけた検討を行う。
Ⅱ.身体拘束最小化のための体制
1)身体拘束最小化チームの設置
身体拘束最小化に向けて身体拘束最小化チームを設置し定期的に会議を開催する。
2)身体拘束最小化チーム
- ①医療・ケアチーム
構成員:医師、看護師(看護部リンクナース:DSTリンクナースが兼任)、MSW、薬剤師、理学・作業療法士、医療安全管理者、医事課 - ②運営方法
定例会議:1回/月 第3水曜日
研修会:1回/年以上
3)身体拘束の当院の現状を定期的に院長に報告する
Ⅲ.身体拘束最小化に向けての基本方針
1)身体拘束の定義
医療サービスの提供にあたって、患者の身体を拘束しその行動を抑制する行為とする。身体拘束その他、患者の行動を制限する具体的行為を以下に示す。
2)身体拘束の具体的行為
(厚生労働省:平成13年3月「身体拘束ゼロへの手引き」から)
- ①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- ④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- ⑤点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- ⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
- ⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- ⑪自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。
3)緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合
患者自身または他の患者の生命又は身体を保護するための処置として、以下の3つの要素を全て満たす状態にある場合は、患者または家族に説明・同意を得た上で必要最低限の身体拘束を行うことがある。
【切迫性】本人または他の患者が危険にさらされている可能性が高いこと。
【非代替性】身体抑制以外に代替する看護(介護)方法がないこと。
【一時性】身体抑制が一時的なものであること。
4)身体拘束禁止の対象とはしない具体的行為
- ①整形外科治療で用いるシーネ固定等
- ②ベッド柵をひも等で固定しない4点柵の使用
- ③点滴時のシーネ固定
- ④身体拘束をせずに患者を転倒や離院などからのリスクから守る事故防止対策
(離床センサー、徘徊センサー等) - ⑤繰り返しの転倒による頭部打撲の保護用具の使用
5)身体拘束を行う場合の対応
緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合は、医師を始め複数のコメディカルで十分に検討し患者または家族に説明・同意を得る。また継続的な観察を行い、診療録に記載し出来るだけ早期に身体拘束を解除するように努力する。
具体的に以下の手順に沿って実施する。
- ①一時的な拘束しか患者の安全を図れないことをチームで検討する。
- ②患者や家族に対し説明を行い、同意書にサインをいただく。
事前にその可能性がある場合はまず口頭で説明し、実際に身体拘束を行う場合は説明し、後日同意書にサインをいただく。 - ③カンファレンスを実施する。身体拘束開始後は最長でも1週間以内に3つの要素【切迫性】【非代替性】【一時性】が満たされているか再評価する。継続する場合も定期的にカンファレンスを開催し、早期の身体拘束解除に向けた取り組みを行う。
- ④身体拘束の種類の変更や中止をした場合、家族に説明する。
Ⅳ.身体拘束最小化のための職員研修
医療に携わる全ての職員に対して、身体拘束最小化に向けての研修会を行い、人権を尊重した医療・ケアの実施を図る。
- 1)医療に携わる全ての職員に向けての研修会を1回/年以上実施する。
Ⅴ.身体拘束最小化の評価
身体拘束が、指針に基づき、適正に実施されているかを定期的に監査し、改善に向けて支援する。
- 1)1回/月リンクナースにより部署の拘束の評価をする。
- 2) 適正な身体拘束が行われているか、薬剤は適正使用されているか、身体拘束最小化チームで必要時院内ラウンドを実施し評価する。
Ⅵ.指針の閲覧について
当院の身体拘束最小化に関する指針は、電子カルテのパソコン内に掲示し職員がいつでも閲覧できるようにするとともに、当院のホームページに公表し患者さま・ご家族が自由に閲覧できるようにする。